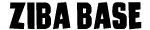鎌倉大日記に書かれていた鎌倉大仏
1498年8月に発生した南海トラフ大地震で発生した大津波で流されたこともある鎌倉の大仏殿。
鎌倉など「倉」を使った地名は裕福な蔵屋敷を連想させ人気な地名の場所となっているが、この倉は「地面がえぐられたような地形」に使われるケースがほとんど。鎌倉の地名は蔵屋敷も倉庫にも全く関係ない。
1923年9月1日の関東大震災級の津波に何度も襲われ続けて作られた釜状の穴倉である。
古文書、鎌倉大日記には下記のように記されている。
「明応四乙卯八月十五日、大地震、洪水、鎌倉由比浜海水到千度檀、水勢大仏殿破堂舎屋、溺死人二百余」
つまり「大地震の津波が大仏殿の堂舎屋を破る、溺死者200人余り」
この「鎌倉大日記」って原本も残っておらず著者も不明な信用性に欠ける日記で信頼性は若干落ちる。いわゆる人づてに聞いた伝言を記した日記のよう。
学者の間では大仏殿近辺まで津波が来たかもしれないが流されてはいないという意見の方が多い。
でも長谷観音前や下馬の浜の大鳥居まで津波が押し寄せたのは確かのようだ。
鎌倉震災史には下馬の延命寺まで津波が押しよせたと記載がある。
全てを知っているのは鎌倉の大仏様だけ。。
昔の地図を見ると海岸線はもっと内陸にあったようだけど海から大仏まで約800m前後。
もし同じ規模の地震が発生したら津波の高さは鎌倉で8~10メートルなので鎌倉の中心地の多くは浸水してしまう。
鎌倉で地震、津波が発生しても落ち着いた行動が取れるようにハザードマップ等事前に確認して、災害時の心がまえを日頃から話し合っておこう。

![]()